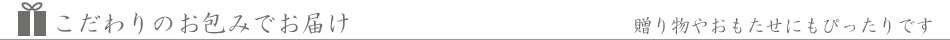村上開新堂は、明治40年に初代村上清太郎によって京都の寺町二条に西洋菓子舗として創業。
大正後期から昭和初期にかけて、各種学校や自治会の菓子の注文百貨店内の食堂の喫茶を任されるなど、古くより国民的に愛されていました。
この「ロシアケーキ」は、戦時中の砂糖配給制の実施による店の休業を乗り越え、日本中が復興に向かって活気づく昭和30年ごろに発売されました。
クッキーより少しソフトな焼き菓子。
アプリコット・レーズン・ブドウジャムサンド・チョコの4種類の味を揃えました。
フレッシュバターの香りと生クリームのコクが広がる、昔から愛される焼き菓子です。
ここがこだわり
御所近く歴史継ぐ洋菓子店

村上開新堂は明治40年(1907年)に寺町二条、現在の地に初代村上清太郎によって西洋菓子舗として創業いたしました。
昭和初期に建てられた洋風の建物は、表が木造漆喰の洋館、奥は和の日本建築と、当時では大変めずらしく最も贅沢な建造物でした。板ガラスのドアやカーブを描くショーウインドウ、高い天井や大理石の柱など当時のまま残されており、明治・大正の面影を色濃く残しています。また、店内に飾られた「開新堂」の書は明治の三筆の一人、日下部鳴鶴の揮毫です。
創業から現在に至るまでの歴史、お菓子の製法や味などの伝統を守りながら、新しい価値への創作をする事でお客様へより良い物を提供出来るよう邁進しています。
商品詳細
-
- 賞味期限:
- 製造日より14日間
-
- 保存方法:
- 常温
-
- アレルギー物質:
- 小麦、卵、乳
-
- 内容量:
- 12枚入り
【原材料】小麦粉・砂糖・バター・卵・牛乳・生クリーム・チョコレート・ベーキングパウダー
【贈答対応】熨斗対応可
-
- 梱包サイズ:
- 4cm x 19cm x 25cm
-
- 温度帯:
- 常温
-
- 商品番号:
- russiacake
店舗名
村上開新堂
村上開新堂のご利用ガイド
送料・配送料について
配送業者:ヤマト運輸 一部配送地域(離島など)や、天候・交通事情によりお届けまで日数をいただく場合がございます。
返品について
☆☆☆ 返品について☆☆☆ ■商品の不良による返品 ご注文の品と違う商品が届いてしまった場合、商品の破損・傷みなどの品質上の問題があった場合には、商品到着の日から3日以内にご連絡いただければ、返品を受け付けます。 【返品条件】 返品をご希望のお客様は、配達日から3日以内にメール・電話にてご連絡ください。4日目以降の返品はできません。 【連絡先】 電話:075-231-1058 担当者:村上彰一 受付時間:10:00~18:00 日祝第3月曜を除く メール:info@murakami-kaishindo.jp 【返送先】 〒604-0915 住所:京都府京都市中京区寺町通二条上る常盤木町62
お支払い方法について
- ■銀行決済
-
【銀行名】三井住友銀行 【支店名】京都支店 【口座種別】普通 【口座番号】584599 【口座名義人名】有限会社村上開新堂 【口座名義人名 カタカナ】ユウゲンガイシャムラカミカイシンドウ 【お振込期限】ご注文日より3日以内にお振込み下さい。
- ■代金引換
-
- 商品価格合計
- 代金引換手数料(税込)
- 0円 ~ 9,999円
- 330円
- 10,000円 ~
- 440円
営業日注意事項について
営業時間/10:00~18:00 休業日/日曜・祝日・第三月曜
会社概要
- 会社名
- 有限会社 村上開新堂
- 住所
- 〒604-0915
京都府 京都市中京区 寺町通二条上る常盤木町62
- TEL
- 075-231-1058
- FAX
- --
同じカテゴリの人気ランキング
この商品を見た人は、こんな商品を買っています
ぐるすぐりでのお買い物は
会員特典利用がお得!
-


- ポイントが貯まる
- お買い物で貯まったポイントは1ポイント1円で使える
-
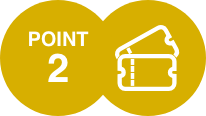

- お得なクーポン
- お買い物に使える会員だけの割引クーポンがもらえる
-


- 最新情報が届く
- 新商品紹介やおすすめ
情報がメールで届く
※ログイン / 会員登録はページ上部の
ログインアイコンやカートページから可能です。
※ふるさと納税におけるポイント付与は
終了いたしました。